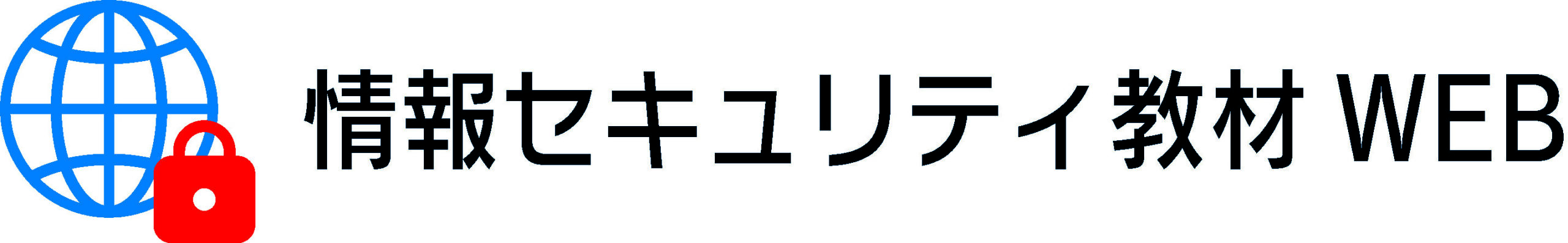中堅・中小企業が狙われる理由① サプライチェーン攻撃

近年、サイバー攻撃のニュースで頻繁に耳にするのが「サプライチェーン攻撃」という言葉です。これは、最終的に大企業や官公庁といった大きな組織を狙うために、その取引先や下請け企業といった“周辺の組織”を突破口にする手口を指します。中堅・中小企業にとっては「自分たちのような規模の会社に攻撃しても大きな利益にならないはずだ」と思いがちですが、実はその油断こそが、攻撃者にとって絶好の隙となっています。
1. 「弱いところ」から侵入するのが合理的
攻撃者は効率的に狙いを定めます。セキュリティ予算が潤沢な大企業のシステムに直接侵入を試みるのは難易度が高いため、まずは防御の甘い中堅・中小企業に目をつけます。そこからIDや業務データを盗み出し、取引先のシステムへ「正規の関係者」を装って侵入するのです。
つまり、中小企業は「最終ターゲット」ではなく「突破口」として狙われてしまうのです。
2. 取引関係そのものが“信頼”に基づく
サプライチェーンには、購買や納品のやりとり、契約情報のやり取りなどが伴います。メールやクラウド上でのファイル共有を通じて日常的にデータが行き交い、「取引先から届いたものだから大丈夫だろう」という心理が働きやすい状況にあります。この「信頼関係」を逆手にとり、偽装メールや改ざんファイルを送り込まれると、大企業側の担当者も気づかずに開いてしまう可能性が高まります。
3. DX・クラウド化で広がるリスクの網
最近では、中小企業でもクラウド型の業務システムやオンラインでの取引が当たり前になっています。便利さの一方で、ID・パスワードの管理が不十分だと不正ログインの危険が高まります。また、委託先のITベンダーが十分なセキュリティ対策を取っていない場合、そこから情報が漏れてしまうケースもあります。攻撃者は一社一社を個別に狙うというより、「どこか1社の弱点を突破すれば芋づる式に広がる」という構造を理解して攻撃を仕掛けてきます。
4. 取引先からの“セキュリティ要求”が増える背景
大企業はこうしたリスクを強く意識するようになり、取引先に対してセキュリティチェックシートの提出や、最低限のセキュリティ水準を満たすよう求めるケースが増えています。もし要求に対応できなければ、取引そのものに影響が及ぶ可能性もあります。
つまり、セキュリティは単なる「防御」ではなく、ビジネスの継続や信頼関係の維持に直結する課題となっているのです。
まとめ
サプライチェーン攻撃は、必ずしも「あなたの会社を直接つぶそう」とするものではありません。しかし、結果として取引先の被害を引き起こし、自社も加害の一端を担った形になる可能性があります。
「狙われるほど価値はない」と思うことは、現代のサイバー攻撃においては危険な誤解です。むしろ、規模が小さい企業ほど狙われやすい“入り口”として利用される現実があります。
自社を守ることはもちろん、取引先を守ることでもある――その意識が、中堅・中小企業に求められる新しいセキュリティの姿勢といえるでしょう。